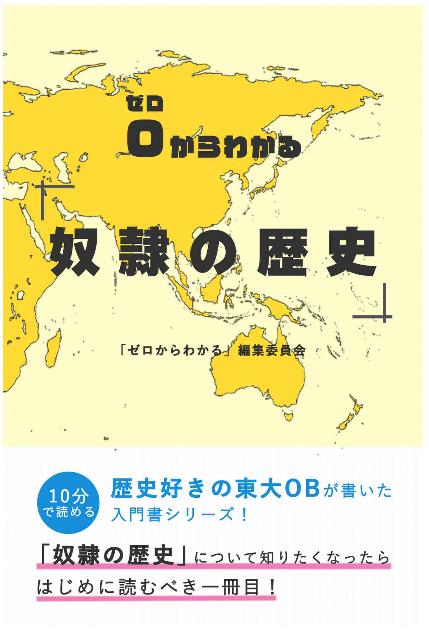鮎といえば夏の風物詩ですが、皆さんはどうやって食べるのが好きですか?やはり塩焼きでしょうか。
今回は、食の巨人・北大路魯山人が語る「鮎の食べ方」を読みながら、贅沢な「洗い」や幻の「鮎めし」について思いを馳せてみました。
この記事のポイント
- 魯山人が推す、新鮮な鮎ならではの「洗い」という食べ方
- 将軍への献上品でもあった鮎の歴史とブランド価値
- 筆者が逃した幻の料理「鮎めし」への未練
鮎の食べ方
- 著者:北大路魯山人
- 初出:1932年(昭和7年)『星岡』
『鮎の食べ方』要約
鮎は水から上げるとすぐに死んでしまう弱い魚という印象があるが、実際は頭をはねてもぽんぽん躍り上げるほど元気ハツラツたる魚だ。
姿は容姿端麗だが、家庭で美味しく調理することは難しい。なにより鮮度の良い鮎が手に入らない。鮎を真に味わうなら、一流の料理屋に頼るほかないのである。
鮎は容姿が美しく光り輝いているほどに味においても上等であり、理想は釣ったものをその場で焼いて食うことだろう。
魯山人は貧乏書生時代、加賀の山中温泉に逗留した際に「鮎の洗い」に出会った。
町はずれの増喜楼という料理屋で、生かしてある鮎が安かったために作ってもらったのだが、これがたいそう美味かったという。
それ以来、人が訪ねてくるたびに増喜楼へ案内して洗いをご馳走したそうだが、たいていの人はあっさりと食わない。
当時高い魚である鮎の頭や骨を(洗いにする過程で)捨ててしまったのかと心配するからだ。
鮎には雑炊や葛の葉巻などもあるが、うっかり食うとやけどするような熱々の塩焼きをガブッとやるのが、やはり香ばしくて最上である。
読んで思ったこと
ホテルで仕事をしていた時、料理のプランとして「鮎めし」が出たことがある。
鯛めしは食ったことがあるが、鮎めしはとんと食べたことがない。
料理人に作り方を聞くと、鮎をひたすらじっくりと4時間ほど焼くことで骨まで食べられるようにし、それを配膳に置かれた小さな釜飯の中に入れて崩して食うのだという。
残念なことにチャンスがまわってこず、プランは終わり食べる機会はなかったが、今でも悔やまれる記憶だ。
将軍への献上品としての鮎
鮎は江戸時代、将軍の食べるものを籠に入れて専門の飛脚が江戸に届けたり、岐阜では鵜飼が捕まえた鮎を鮨にして献上したりしたこともある魚である。
日本全国どこでもとはいわないが、そういった話は東京周辺に残っている。
食べ方を聞かれれば、100人中99人は「塩焼き」と答える魚ではあるが、縄文時代から食べられている歴史ある魚なのだ。
しかしながら、現代において食べ方の選択肢がほぼ一択しかないというのは、少々寂しい気もする。
「洗い」という贅沢と正統派
魯山人が好む「洗い」という食べ方だが、今まで川魚を刺身にして食べるのは向いていないのではないかと考えていた。
しかし、よく考えてみれば鮭(サケ)と同じようなものだと捉えれば、刺身で食べるということも出来るのかもしれない。
もちろん、寄生虫のリスク管理や鮮度が命となるため、魯山人が言うように「生かしてある鮎」を使える環境でしか許されない贅沢なのだろう。
鮎を食べられる場所は、田舎では今でも探せばあるだろうが、都会ではなかなかの高級魚だったようだ。
魯山人が本の中で「京都では2円という価値がある」と書いていることからも、その特別感が伺える。
色々と想像を巡らせたが、やはり鮎は塩焼きにして食べるのが正統だと思う。
熱々の身をハフハフと言いながら食べる、あの香ばしさこそが鮎の真骨頂なのだ。