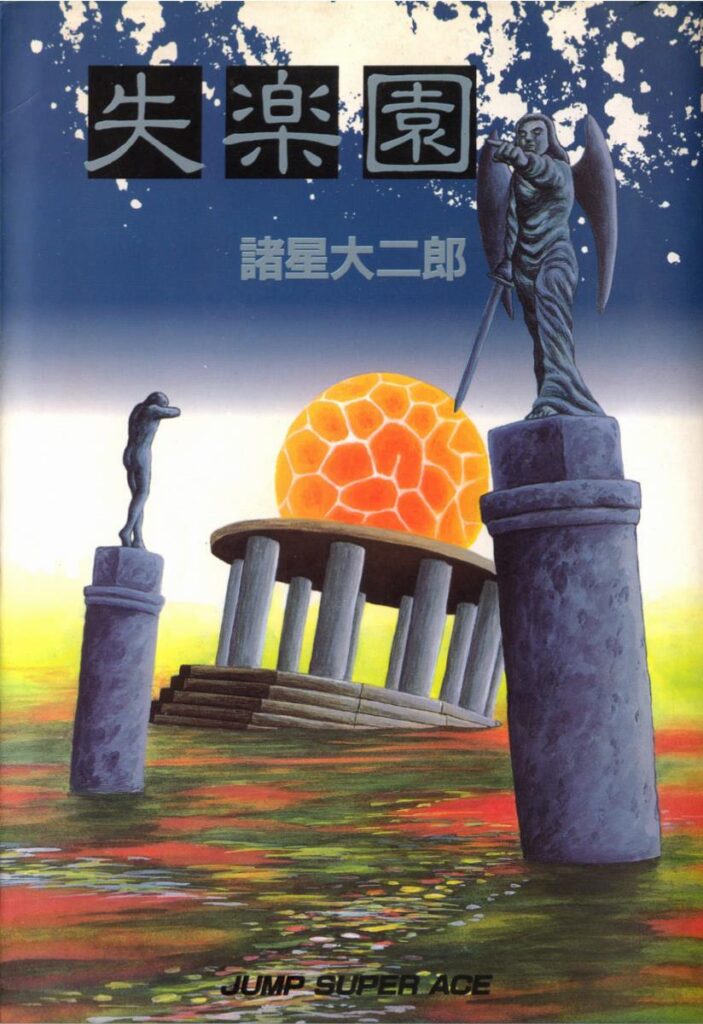狐古さやかさんの人生初の単行本『穂高輪花のチャリと飯。』自転車よりもレーパンと食事姿を愛でる漫画

漫画のジャンルとして
自転車、グルメ、女性主人公、レポート、服装、実在のお店
とりあえずここから1話が読めるので『穂高輪花のチャリと飯。』
1話目の冒頭で主人公である穂高輪花が書いていた小説にはセックスのあとにピザを食べると言う。しかしそれを書いていた本人はそれよりも美味しくご飯を食べる方法があると思い立ってスタート。本格的なサイクルジャージを着て本格的な自転車であるロードバイクで50kmもの距離を走ってピザを食べに行く。ロードバイクで走った疲労感と空腹感がご飯を美味しくなる。
漫画の1話は読者が漫画をどんな視点で読むかを決める重要なステップ。1話目を読むことで主人公である彼女の生活や仕事、そして漫画の主題や作者が描きたい絵は何かが見えてくる。
「穂高輪花のチャリと飯。」の1話目はセックスよりも食事が美味しくなることはなにかという人間の根源的欲求である性欲からの食欲よりもロードバイクと走ったあとの疲労感と空腹感からの食べる食事が優っているというストレートな読み方をした。

1話目でピザを食べる姿は12ページの中で3ページも割いている。ロードバイクに乗って生まれた空腹感を満たしてくれる濃厚なチーズ、猪肉の旨味に塩加減が丁度いいとかなりご飯について詳しく語っていること姿もご飯を噛み味わっている描写として食べて口を動かしている擬音と唇を波うつシーンを描くことでしっかりご飯を味わった感想を言っているレポートと表現されている。
1話を読めばご飯を美味しそうに食べていること、実在するお店の紹介としての面があり、漫画のあとには紹介レポートも付いている。ロードバイクで走って空腹になって食べるご飯は美味しいということは伝わってくる。
『穂高輪花のチャリと飯。』はロードバイクがメインではなく、ロードバイクに乗っている人物と走った先で食べるご飯。
1巻に収録されている10話の中には主人公である穂高輪花の生活でロードバイクが中心となって回っているかは雨の日に家の中でロードバイクを走らすための機械の購入を考えたり、表紙でもわかるように彼女の腕の3倍程もある太ももは自転車をほぼ毎日のように乗っている人の筋肉として描かれている。
『穂高輪花のチャリと飯。』は主人公である穂高輪花のロードバイクを乗っているシーンと美味しそうな料理とその味のかたりを読めばいいと思って読んだ。
作品に出てくるお店の美味しそう料理とレポートを読めばそのお店に行ってみたいと思うし、爽快に走っているロードバイクを見ていると同じように走ってみてもいいかなと考えてしまう。
視点を変えたもう一つの読み方もある。
そんな読み方をしたが、1巻のラストの2ページまで読んでいると、10話に登場する少年が語る。
少年は穂高輪花のご飯を食べる姿とレーパンとサイクルジャージを楽しむのだと、少年が子供の頃にその姿を見て性的興奮を初めて感じたと恍惚の表情で語っている。
フロイトは欲求は性欲を起点にしているという話をしているが、原始的な欲求である食欲から性的な欲求を感じるのは間違えではなく。
・ご飯を食べる姿
・レーパンとサイクルジャージの姿

この2つを見てリビドーに目覚めたと少年は言っている。
読み返してみると食事のシーンはだいたい顔のアップと口のアップのコマが多く、食べ物を口に入れる瞬間、食べ終わったあとの料理の美味しさを表現としての口を開けての喜びの顔食事のときの歯と舌が細かく表現される。
さらりと読んでしまうと擬音とご飯の味の感想の文字での説明に目を取られてしまい食べている人物の表情にはさっと目がはしるだけで流れてしまっている。食べている表情は口だけではなく、顔の角度や食べ物を噛んでいる表現は味わっていることをわかるように目が細くなるといった微細な変化がつけれていることに気付く。
穂高輪花のレーパンとサイクルジャージの姿を意識しながら読み直してみるとロードバイクを走らせている姿よりも、コマをぶち抜いての立ち姿で全身をできるだけ見えるようになっていて、見せたい姿はこれとわかってくる。
立ち姿はロードバイクに乗っている場面ではなく食事中や自転車から降りたあとの姿でレーパンとサイクルジャージを見てくれと言わんばかり。
レーパンのミシン目とかをここまで強調して描いている自転車マンガはかなり珍しいと思いつつ、マンガの読み方は色々あるけれど、色目を意識した視点でマンガを見なくなってるなと思った。
1話だけを読んだときは3ページ目までに性的な小説を書いていたり、穂高輪花がレーパンとサイクルジャージに着替えている場面があったりと単行本が出る前に1話だけを読んだときは大人向けの雑誌によるような印象を感じたけれども1巻を通してみるとそんな印象が消えていたことに驚いた。