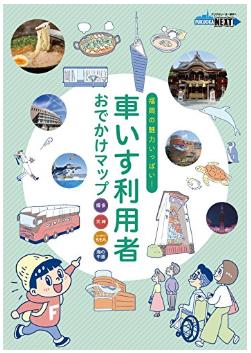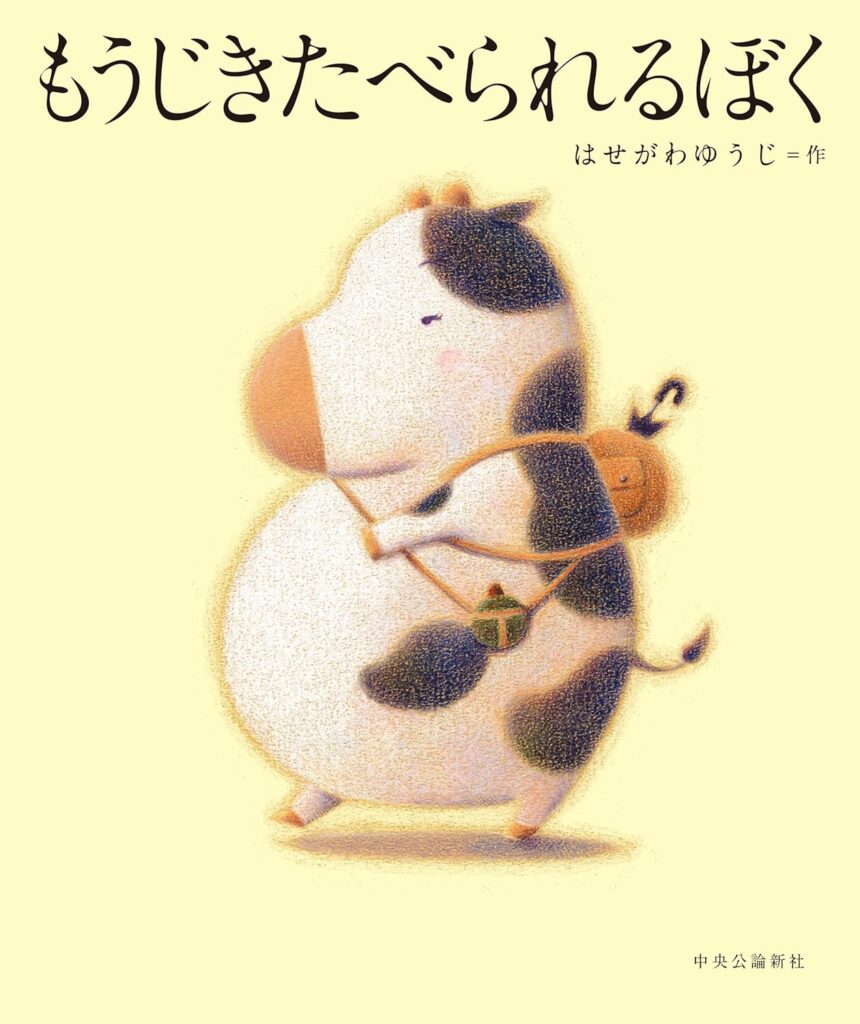1954年(昭和29)、「芸術新潮」に掲載された手記。手記というよりは、旅先からの手紙をそのまま掲載したような生々しさと、魯山人ならではの歯に衣着せぬ物言いがあります。
ふと、戦後間もないアメリカの食事情を、日本の食通はどう感じたのか読みたくなりました。
この記事のポイント
- 戦後アメリカの「味気ない豊かさ」に対する魯山人の辛辣な評価
- 現代のコンビニ文化を予見した「ドラッグストア」への洞察
- 正しい手順を知らなくても広まる「日本料理」のたくましさ
アメリカの牛豚
- 著者:北大路魯山人
- 初出:1954年(昭和29)「芸術新潮」
『アメリカの牛豚』要約
シカゴでの話。アイルランド人の経営している料理屋で食べたロブスターは伊勢海老に近い種類のようだが身が締まりすぎていて味がない。
ニューヨークでもアイルランドの料理店に行ったが、ここでは客が陳列さている中から好みの料理を食べるスタイル。しかし鮮度がなく、不潔にさえ思えて食べる気がしないのでビーフステーキを頼むと、焼き方は良いけど味はいまいち。ただしサイズだけは日本の3倍はあった。
魯山人が言うには、アメリカの牛豚の肉はどこでもあまり美味しくなく、合格点を出せるのは羊の脇腹の肉ぐらい。卵もミルクもよくない。
ニューヨークの印象として、アメリカ人は食欲があるのに、ひどく事務的に食事をするように見えたそうだ。
ドラッグストアと「なんちゃって」日本料理
町には1ブロックごとにドラッグストアがあり、此処では薬ばかりか日用雑貨やソーダ水、食事まで出来るようになっている。
食堂はスタンド式が多く、たいていハンバーグとケーキを食べ、オレンジジュースを飲んだ客が雑踏に消えて行く。
ニューヨークのイタリア料理店「マルキ」はお酒とソーセージがうまかった。とくにリング(たらの類)という魚の唐揚げが美味しかったという。
極めつけは「都」という日本料理屋。すきやきが出たが、鍋のようにゴチャゴチャで魯山人は驚いた。
主人に聞くと新潟生まれで、東京にも行ったことがないという。
参考のために魯山人がすきやきの模範を示したところ、「へェー、すきやきというものは、そういうふうにして作るものですか」と目を丸くしていた。
読んで思ったこと
なぜこの内容が文芸誌である「芸術新潮」に載ったのかはなかなかに謎だが、内容はとても興味のつきぬものだ。
ロブスターと牛肉のステーキは口には合わなかったようだが、なぜ『アメリカの牛豚』というタイトルなのかも気になる。
鮮度と食文化の違い
料理や卵、ミルクの鮮度に関して、日本とは違い大きな都市の文化になるとどうしても落ちてしまうものだったのだろう。
冷蔵庫の普及率や物流事情もあっただろうが、ほとんどが常温で販売されている時代の鮮度など推して知るべしである。まして大都会であるシカゴやニューヨークなのだから。
お肉も日本と違い赤身の文化なので、日本の牛のようにある程度脂を持った品種でないことも、魯山人の舌に合わなかった理由としてあるのかもしれない。
ドラッグストア文化の萌芽
それよりも面白いのはドラッグストアの話だ。
ソーダ水が販売していたとのことだが、ペプシもコーラもドクターペッパーも、元々はアメリカのドラッグストアで薬剤師が調合して独自に販売していた飲み物が拡大していったものである。
アメリカの文化を語る上で、ドラッグストアは忘れるわけにはいかない。
とりあえず、行けばなんでもある。現代のようなコンビニをかなり拡大したお店であったことは確かだろう。
正しい手順を知らない強さ
一番パンチが効いているのが、新潟生まれの主人がやっている日本料理屋「都」のエピソードだ。
魯山人が亭主に聞いたところ、東京には行ったこともない人物のお店らしい。
魯山人のすきやきの模範を見て初めてすき焼きの作り方を知ったというのは、いま世界中に広がっている「カリフォルニアロール」のような寿司や、現地の味噌汁と同じ現象だ。
正しい手順の料理を知らなくても、なんとかなるし、商売として成り立ってしまうという事実が面白いのである。