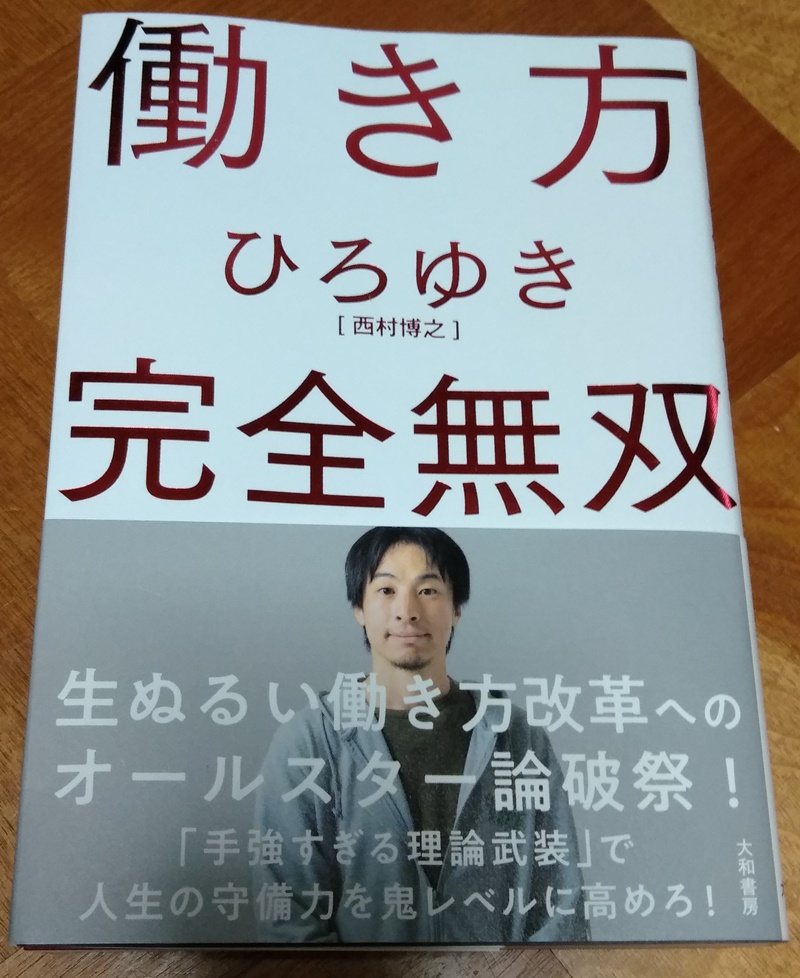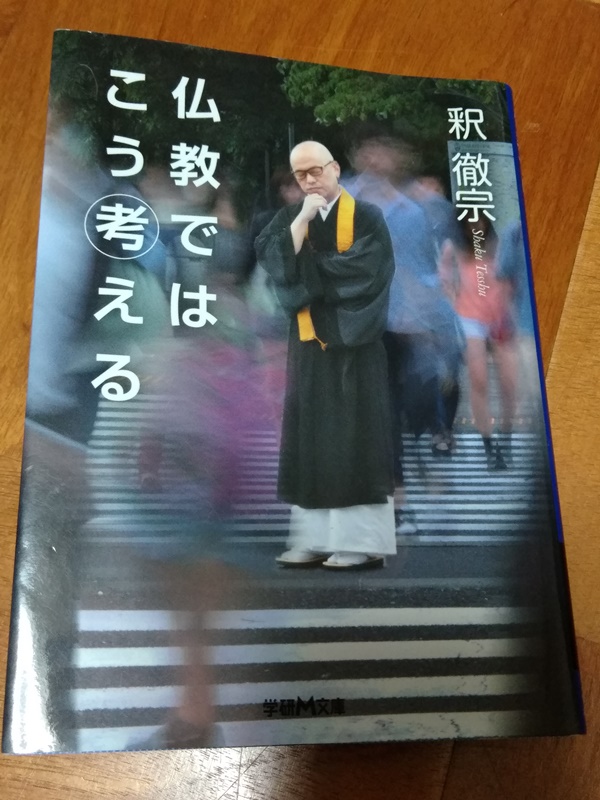北大路魯山人『味を知るもの鮮し』を読みました。短い随筆なのに、「うまいものを食べる」って案外むずかしいのだ、と背筋が伸びます。
この記事では、内容を短く要約したうえで、魯山人が強く嫌う「砂糖」「化学調味料」、そして最後に出てくる「器」の話を、僕の言葉で整理します。
とりあえず内容を要約していますが、読んだ僕のフィルターを通していることをご了承ください。
この記事の要点
・『味を知るもの鮮し』の主張をざっくりつかむ
・砂糖と化学調味料に厳しい理由が分かる
・最後に「器」を置くのが魯山人らしい
味を知るもの鮮し
- 著者:北大路魯山人
- 形式:随筆(エッセイ)
- 読む方法:青空文庫(無料)、または各種文庫本
『味を知るもの鮮し』の要約
魯山人はまず「毎日、朝昼晩とうまいものを食べたい」と言います。うまいものを食べれば人は機嫌がよくなる。そんな食生活が健康の源になる。ここが出発点です。
世間ではカロリーだとかビタミンだとかが大事だと言う。でも、それだけを考えて食べると心の喜びがない。自分が「うまい」と思うものを食べて、三食ともちゃんと楽しめたら、それがいちばん良いのだ――魯山人はそういう感覚で書いています。
それなのに貧しい人は仕方ないとしても、豊かな人まで食を自由にしていない。似たようなものばかり食べている。日本にはうまい食材が千以上あるのに、実際に口にするのは50か100そこら。驚くほど無関心で、どの家庭もだいたい「偏食」を続けている、と。
砂糖と化学調味料、そして器
魯山人は「家庭で本物の日本料理を作れる人はほぼいない」とまで言います。ラジオの料理もレベルが低い。色や香りや味に対する経験が薄い人が料理関係者に増えている。だからもっと厳しく改めてほしい――かなり手厳しいです。
ただ、言っていることははっきりしています。鮮度のよい素材の持ち味を生かせば、化学調味料に頼らなくても十分うまい料理は作れる。間違っても無用に砂糖を使うな。砂糖は劣等な食品をごまかす秘密を持っている、とまで言い切ります。
そして最後に「器」。うまい食事を作るには、よい道具、よい食器が必要だ。器がよいと味がよくなる。品のよさがあれば、口にうまく、心に楽しく、栄養の面でも届く。味を“口の中だけ”に閉じ込めないのが魯山人らしいところです。
読んで思ったこと
栄養の理屈が整うほど、「うまい」はこぼれやすい
昭和33年頃は、栄養の研究が進んで「人間の体に何が必要か」が見えてきた時代です。便利になった分、食を数字で語りやすくもなった。
でも魯山人は、そこに首を振る。カロリーやビタミンを否定したいわけではなく、「それだけで食を済ませるな」と言っているのだと思います。
うまい食材をまんべんなく食べれば、体と心の栄養は自然に足りる。乱暴に見えて、筋が通っている。食は、生活の手ざわりそのものだからです。
高度成長期の「便利さ」に、魯山人はブレーキをかける
高度成長期に入って、洋食がかっこよく見えたり、化学調味料が当たり前になったり、砂糖が簡単に手に入るようになったりする。さらに「食事に時間を使うくらいなら別のことをしたい」人も増えていく。
魯山人が苦々しく見ていたのは、便利さそのものより、その便利さに慣れすぎることだと思います。濃い味に寄りかかると、素材のやさしいうまさが聞こえにくくなる。気づかないうちに、舌が鈍るのです。
成人病(生活習慣病)と、食の乱れ
当時は成人病が話題になり始めた頃でもあります。食事制限が必要な人が増えていく。魯山人はそこを「食の乱れ」の結果だと見ている。化学調味料や砂糖の乱用が、体を壊していると。
ただ、ここで終わらないのが魯山人で、「そんなものに頼らなくても、日本の山と海には十分うまいものがある」と言い切る。責めるだけで終わらせず、視線を素材へ戻す。ここに救いがあります。
最後に器を置くのが、いちばん魯山人らしい
どうすればうまく食べられるかの話として、最後に器を出してくる。味を口の中だけの話にしない。見た目、香り、手触り、食べる場の空気まで含めて味だと考えている。
だから、器はぜいたくではなく「食べ方を整える道具」なのです。食を丁寧に扱い切る。その姿勢が文章の末尾に残ります。